食事制限が歯に与える影響はある?ダイエットと口内環境の関係を解説
2025/01/20

こんにちは、成田市の歯医者、メイプル歯科はなのき台クリニックです。
ダイエットは、美容や健康維持のために多くの人が行うものですが、食事制限などが口内環境へ影響を与えることはあるのでしょうか。
また、影響を与える場合、どのような影響なのでしょうか。
食事制限を中心としたダイエットが、口内環境にもたらす良い面と悪い面を解説します。
ダイエットが与える、口内環境への悪影響
必要な栄養素が足りなくなる恐れがある

歯や骨の健康を保ち、その機能を維持するためには、カルシウム、たんぱく質、ビタミンD、マグネシウム、リンをはじめとしたさまざまな栄養素が必要です。
カルシウムは歯や骨の主要な構成成分であり、これが不足すると歯の硬度が衰え、虫歯や骨折を招く恐れが高まります。
たんぱく質は、歯ぐきやあごの骨を支える組織の再生をサポートし、不足すると歯周病の進行を助長してしまいます。
ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、強い歯と骨の形成を助けます。
また、マグネシウムやリンも歯や骨の構造を強固にするために欠かせません。こうした栄養素の不足は、口内環境の悪化を招く恐れがあるため、ダイエット中でもこれらの栄養素は意識的に摂取する必要があります。
ストレスで歯ぎしりや食いしばりが起こるリスクがある
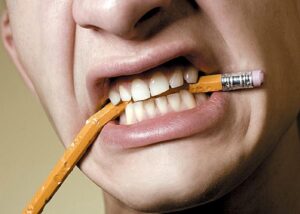
ダイエットにより厳しい食事制限や激しいトレーニングを行っていると、心理的なストレスや不安感が増すことがあります。
これが継続すると、無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをするようになり、結果的に歯やあごに過度な負担をかける可能性があります。
歯ぎしりや食いしばりは、歯の摩耗による虫歯の発生や歯ぐきへの負担による歯周病の悪化、顎関節にかかる負担を増加させることによる顎関節症の発症につながります。
また、運動中に無意識に歯を食いしばっているという場合にも注意が必要です。
唾液量が減ったことによる口臭の悪化

唾液は、口内を洗浄し、口臭を引き起こす菌の発生を抑制する働きを持っています。
そのため、食事制限などの極端なダイエットにより唾液の分泌が減少すると、これらの抑制機能が働かなくなり、口臭の悪化につながります。
これを予防するためには、日常的に水分をしっかりと補給し、食事の際にはしっかりと食材をかんで唾液の分泌を促すことが重要です。
また、唾液腺を刺激するために酸味のある食材を摂取するのもおすすめです。
炭水化物を制限したことによる口臭の悪化
極端に炭水化物を制限するダイエットは、体のエネルギー源を変えることで特有の口臭の原因となることがあります。
通常は、体は炭水化物を摂取すると、それを消化して得られるグルコースをエネルギー源として利用します。
しかし、ダイエットにより炭水化物の摂取量が少ない場合、体内の脂肪を分解して「ケトン体」を生成するようになり、これが原因で「ケトン臭」と呼ばれる特有の口臭が生じることがあります。
「甘酸っぱい」と形容されることも多いケトン臭は、口臭のほか体臭となって現れることもあります。
このにおいを緩和するためには、炭水化物も適度に摂取することや、食事制限だけではなく、筋トレや有酸素運動なども取り入れたダイエットを行う必要があります。
ダイエットが口内環境に与える良い影響
糖分の摂取制限による虫歯のリスク低下
ダイエットが与える口内環境への良い影響としてまず考えられるのは、糖分の摂取量の減少です。
ダイエットの一環として糖分の摂取を制限すると、口内のpHバランスが改善され、虫歯の原因となる細菌の活動が抑制されます。
結果として、エナメル質の損傷が減少し、虫歯の発生リスクが低下します。
さらに、糖分の摂取が少ないと、唾液の浄化作用がより効率的に働き、口内の健康を維持しやすくなります。
歯や歯ぐきに必要な栄養素の摂取量が増える

ダイエットを通じて摂取量が増えることの多い野菜や果物は、口内の健康においてもいい影響を与えます。
これらの食品には、体内の酸化ストレスを軽減する抗酸化物質が多く含まれており、ビタミンCやカルシウムといった栄養素が歯ぐきや歯の健康をサポートしてくれます。
ビタミンCはピーマンやブロッコリー、イチゴ、キウイなどに、カルシウムはケールやホウレン草、チンゲン菜、イチジク、ナッツ類などに多く含まれています。
食物繊維が含まれた食材の摂取量が増える

食物繊維の多い食事は、咀嚼を促進し、それによって唾液の分泌量を増加させる働きがあります。
唾液には口内の汚れや細菌を洗い流す作用があるため、歯垢の蓄積を防ぎやすくしてくれます。
また、ゴボウやセロリといった繊維質の食材は、かむことで歯の表面の汚れを清掃してくれるため、その点でも虫歯予防につながります。
歯周病と肥満の関係

歯周病と肥満には相互関係があると考えられており、その要因の一つが脂肪細胞で生成される炎症性サイトカイン「TNF-α」です。
「TNF-α」は、歯を支える歯槽骨を溶かす作用があり、これが歯周病の発症と進行を助長すると考えられています。
また、肥満が引き起こす免疫力の低下も歯周病の発症・進行に影響すると考えられています。
そのため、肥満を改善することは、生活習慣病はもちろん、歯周病の予防にもつながります。
歯周病と生活習慣病の関係
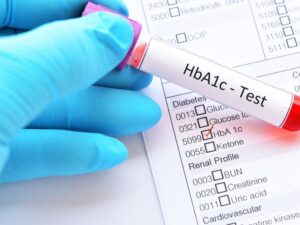
歯周病による慢性的な炎症は、インスリンの作用を低下させ、糖尿病のコントロールを難しくすると考えられています。
また、歯周病の影響により心血管系の健康が損なわれると、心臓病や脳卒中のリスクも増大すると考えられています。
さらに、歯を失って咀嚼能力が低下したことで食生活が偏ってしまい、高血圧や脂質異常症のリスクを招くこともあります。
これらを防ぐためには、口内の健康を保つこと、そして生活習慣そのものを改善し全体的な健康を向上させることが重要です。
まとめ
ダイエットを行う際は、単に体重を減らすだけでなく、全身の健康や口内環境をも視野に入れたアプローチを行いましょう。
過度な食事制限による栄養不足は、口内の健康状態を悪化させ、歯や骨に長期的な影響を与える可能性があります。
また、肥満や歯周病は生活習慣病との関連も強く、これらを予防し全身の健康を守るためには、口腔ケアとともにライフスタイル全体を見直すことが重要です。
健康的な生活習慣を取り入れることこそ、長期的な健康維持の鍵といえるでしょう。
メイプル歯科はなのき台クリニック :https://maple-dental-clinic.jp/
〒286-0007 千葉県成田市はなのき台1-22-8
電話:0476-27-4618


